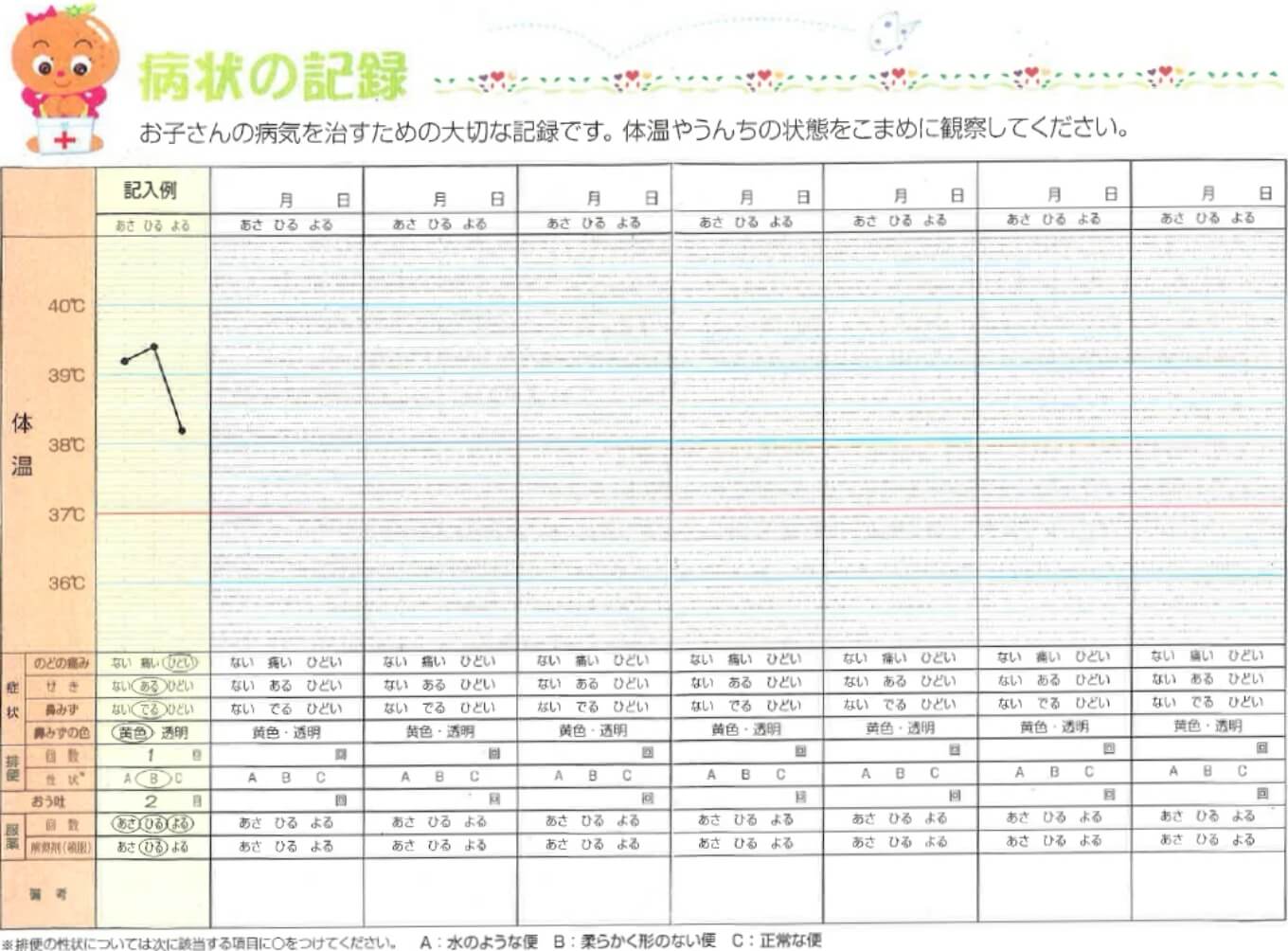今月の独り言
寒い1月
1月半ばからすごく寒くなりましたね。
関西の都市部でも雪が積もったりして、ずっと寒波が続いています。
寒くなったせいもあってインフルエンザが流行してきました。どうも、かかりやすい人とそうでない人とあるようで、ウイルスに感染しやすさは個人差があるといわれています。ワクチンをしているのに毎年かかるという子と、ワクチンなんかしなくても何年もかかったことがないという子と。でも、ワクチンは絶対かからないというわけではないですが、明らかに症状を軽くします。高熱にならなかったり、しんどさがあまりなかったりして、普通の風邪と見分けがつかず、検査をしてみたらインフルエンザ陽性ということがよくあります。
それから、体内に入ってきたウイルス量が少ないと、ワクチンをしていれば感染をブロックできます。家族内では接触が密接ですから感染を防ぐのは難しいですが、クラス内や電車の中の感染は防げる可能性が高い、ということです。今年はワクチン終わっちゃいましたが、また来年!
インフルエンザにかぎらず風邪の予防は、うがい、手洗い、マスクです。とくに電車や人混みでは気をつけましょう。
まだまだ寒いです。春が来るまでがんばりましょう。
2016年の暮れです
昨日で今年の診療を終えました。年明け1月3日まで休ませていただきます。
今年は、開業10年目の節目の年でした。子どものアレルギーの専門治療を、身近な診療所でやりたい、という気持ちで始めて、いろいろ大変なこともありましたが、なんとかやってこられました。たくさんの、いろんな患者さんとご家族と、長いお付き合いができて幸せなことに、今の仕事を続けていられます。優秀なスタッフにも恵まれ、患者さんの立場にたった医療をしたいという気持ちを支えてくれています。また、10月から一緒に仕事をしている海老島先生は、本当に頼りになる優秀なドクターで、食物アレルギーのプリックテストなど、私があまりやっていなかった分野もしてくれています。とてもいい後継者に恵まれてよかったと思っています。アレルギーだけでなく、小児科一般の患者さんも増えてきて、育児に真剣にとりくむお母さんたちとの話もいろいろできて、改めて、小児科医になってよかったなと思うことも増えました。何より、子どもたちの笑顔が私たちを支えてくれます。
まだまだ私もがんばりますが、年を重ねるといろいろしんどいことも増えてきて、弱音をはきたくなることもあります。来年は、体も鍛えて、また新たな気持ちで歩んでいきたいと思います。
皆さま、どうぞよろしく。よいお年をお迎えください。
ワクチンを受けよう
先日受診された赤ちゃんが、1歳になるのに、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチン1回受けたきりで後が途絶えているのでお母さんに訳を聞くと、ワクチンは危ない、受けないほうがいい!という内容の本を読んだそうです。その本を書いたひとが、ワクチンなしで生きていく子どもを大人になってからも一生、責任をとってくれるというのでしょうか。
30数年前研修医一年目で私の担当患者さんの死亡1例目は、はしかの脳炎の5歳の女の子でした。はしかは、自然経過でも1週間ちかく高熱が続き大変な病気ですが、合併症が多く死亡率も高いので、定期接種になって社会で根絶を目指している病気です。肺炎や中耳炎は約7%に合併します。脳炎は0.1%に合併し、致命率が高いのです。いったん発症すれば、治療法はありません。その女の子も、はしかになったあと熱が下がらず、けいれんが続き、意識不明になってほかの病院から搬送されてきたのです。けいれんは止まり、熱は下がりましたが、意識は戻らず寝たきりで、1か月で亡くなりました。主治医の私の役目は毎日3回病室に行き、ずっと付き添っている両親やかわるがわる見舞いにくる祖父・祖母や親せきのひとたちが、枕元でその子に呼びかけたり、その子がどんなに明るくいい子であったかを涙ながらに語るのにじっと耳を傾けて悲しみを共有することでした。はしかは予防するほかないのです。
私の研修医時代死亡2例目はダウン症の男の子で、肺炎で入院して、二日足らずであっという間に亡くなってしまいました。今ならワクチンで予防できる肺炎球菌の肺炎でした。
その当時小児科医は、救急当番をするとき、数多く来る乳児の発熱から細菌性髄膜炎を見逃さないことが使命でした。数時間診断が遅れると、けいれんが止まらなくなり悲惨な経過をたどります。1/3は助かるが、1/3は後遺症が残り、1/3は死亡するといわれていました。私と同僚は研修医1年目であわせて5人の細菌性髄膜炎の治療にあたりました。幸い全員が後遺症なく治癒しましたが、あの当時全国で1000人以上が発症していたと思います。今は、ヒブと肺炎球菌のワクチンで病気が激減しています。
先天性風疹症候群は、妊婦さんが風疹にかかると心臓・眼・耳に障害がある赤ちゃんが生まれる病気です。日本では1977年から1995年まで、女子にしか風疹ワクチンをしておらず、免疫のない男性を中心に風疹の流行が繰り返され、そうなるとワクチンを受けていないあるいは抗体がうまくつかなかった女性から何人も先天性風疹症候群の赤ちゃんが未だに生まれているのです。生んだお母さんが悪いのではない、日本のワクチン行政の甘さが生んだ事象です。
そのほか、出産直前に水痘にかかった妊婦さんから生まれた赤ちゃんが生後激烈な水痘で死亡したのも見ましたし、患者さんのお父さんで、大人になってかかった風疹で亡くなった人もいました。おたふくかぜにかかって、合併症で難聴になったお子さんも何人か知っています。
ワクチンは、子どもたちを守っているのです。開発途上国ではなく、日本でワクチンの恩恵を受けているのですから、ぜひちゃんと受けさせてあげてくださいね。そういう話をすると、冒頭のお母さんも、ワクチンの予約をとってかえられて、ほっとしました。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL