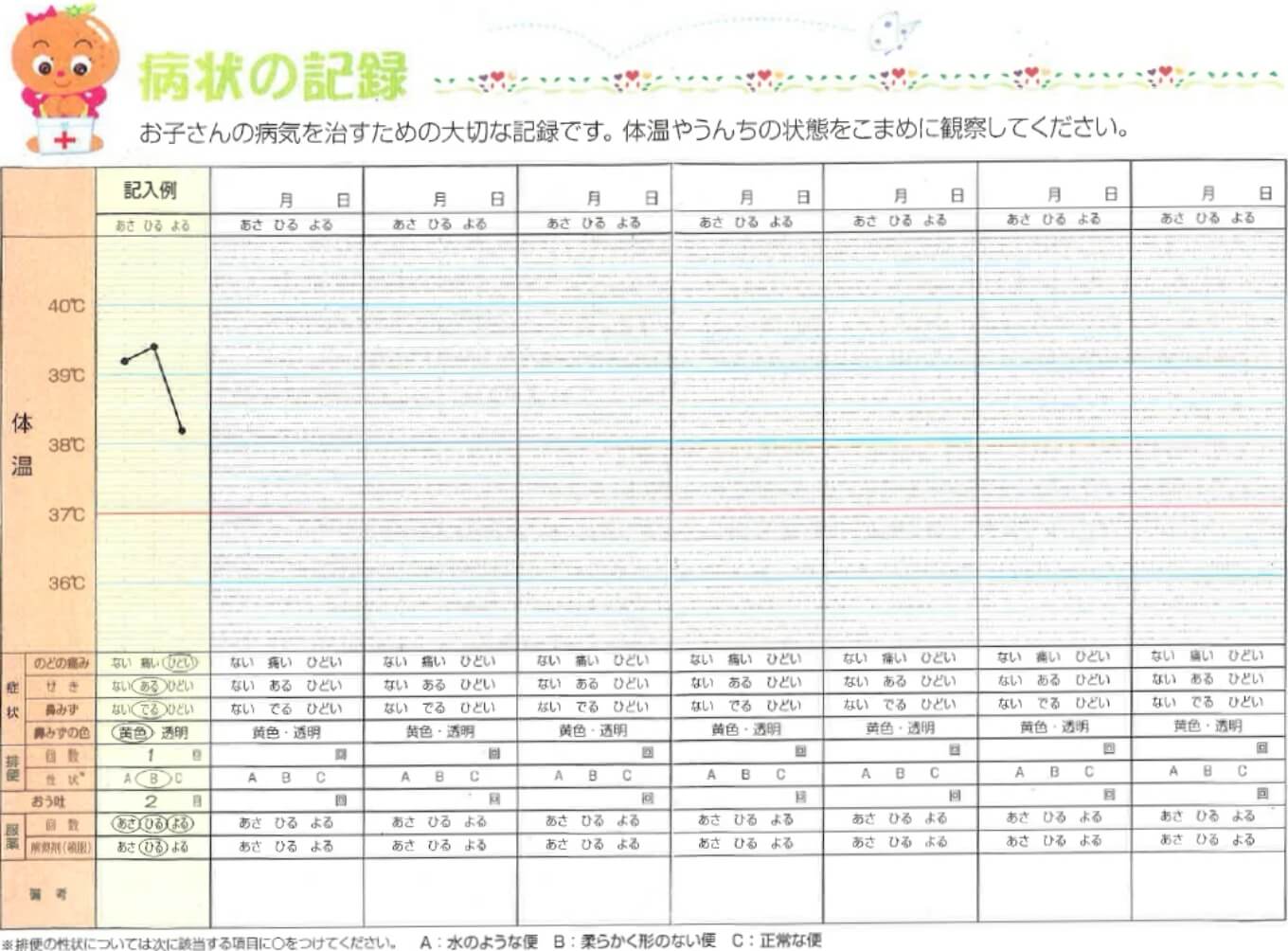今月の独り言
夏かぜって?
早々と梅雨が明けて、暑い夏がやってきました。小児科の外来では、発熱のお子さんの受診が増えていますが、何といった病気ではなく、夏かぜが多いです。
インフルエンザやアデノなど検査しても陰性です、というと、あ、じゃ感染症じゃないんですね、とおっしゃる保護者さんがいらっしゃいますが、いやいや感染症ですよ、原因病原体がわからないだけで。病原体の名前のついた病気だけが感染症と思っていらっしゃるのですね。
小児の発熱のほとんどは感染症によるものです。熱中症の発熱は感染症ではないし、白血病や膠原病など全身疾患で熱が出ることはありますが、全体から見るとまれなものです。ウイルスや細菌が体の中に入ると、体はまず熱を出して反応します。そのあと熱がどのくらい続くか、他にどんな症状が出るかは、原因の病原体によるのです。
はしかや風疹、百日咳、水ぼうそうなどは病態がはっきりわかっている病気で、重症になる、合併症がある、ということでワクチンがつくられ、しっかり接種してもらうとほとんどかからないし、流行もほとんどないのです。
夏かぜというのも、ウイルスによる熱をともなう感染症ですが、症状が軽くて自然に治ることが多いので、ウイルスの検出もしないし病名もつかないのです。ヘルパンギーナや手足口病は夏に流行するウイルスの感染症なので、夏かぜの一種といってもいいかもしれません。ヘルパンギーナはのどに発疹がでて、発熱と咽頭痛が強く、原因はコクサッキーAウイルスです。手足口病は、手のひら、足のうら、のどに水疱疹ができ、原因はコクサッキーやエンテロウイルスです。このふたつは症状で診断がつきますが、原因ウイルスを検出する方法は一般にはありません。
咳や鼻水がすこしあって熱が1~2日出て、わりと元気で治っちゃうものを私は夏かぜといって患者さんに安心してもらうようにしています。
5月のおでかけ
5月はあちこち遊びに出かけました。
名古屋まで久しぶりにクラシックのコンサートに行きました。世界的指揮者の佐渡裕さんがウィーンのオーケストラを率いて来日し、マーラーの交響曲第5番という大曲を演奏しました。2021年のショパンコンクールで2位になった反町恭平さんがゲストで、モーツァルトのピアノ協奏曲23番、これもよかった。その日は興奮さめやらず名古屋に泊まって、翌日は朝から大阪へ出勤しました。
白浜のアドベンチャーワールドのパンダが来月中国に返還されるというので、この前の日曜は白浜までパンダを見に行きました。人は多かったけどゆっくり4頭見られて、なんてあんなに可愛いんでしょうね。そっくりかえって座って竹をむしゃむしゃ食べていました。いなくなると寂しいね。
先週末は熊本で同窓会でした。卒後42年になりますが、熊大医学部卒の女子だけが、17人中11人も集まりました。みんな大学や病院や施設のお医者さんしていて、定年になって週2~3日の仕事、というところ。みなバリバリに女医さんしてきてますが、今週5で働いてるのは3人のみ。意外にも自分で開業しているのは私だけでした。いっぺんに学生時代に戻ったようなにぎやかさで楽しかったです。私も来年で開業20年になります。ちょっと体力的にきつくなってきていて、そろそろ仕事を減らそうかと思いました。
はしかはこわいよ
今年麻疹(はしか)が流行していると伝えられています。現在2025年で78例の報告があります。
麻疹は2000年に定期のワクチン接種が始まってから発症が激減していました。麻疹は空気感染をし、感染力が強く、有効な治療法はありません。ワクチン接種で免疫をつけるしかないのです。最近の麻疹の発症はワクチン接種をしていない人ばかりで、ワクチン接種の進んでいない海外での感染、もしくは外国人の感染持ち込みがほとんどです。
昔ははしかは、病気になってそれで免疫をつけるものでした。水痘も百日咳もおたふくかぜもそうです。でも一定数の子どもが合併症で命を落としたり後遺症が残るのです。麻疹は発疹と高熱がつづく病気で、その状態自体もしんどいのですが、多く中耳炎や肺炎を合併し、1000人に1人は脳炎の合併があります。治療法はなく、脳炎になると1/3は死亡、1/3は後遺症が残り、1/3が回復するといわれていました。
私が40数年前小児科医になって初めて担当して死亡した患者さんは4歳の麻疹の脳炎の女の子でした。麻疹罹患後脳炎でけいれんが止まらず、私のいた小児専門病院に搬送されたときは、けいれんは止まっていましたが意識のない状態でした。何も助ける薬はありません。いっぺんも目覚めることもなく、数日で亡くなりました。何もできないという無力感は今も忘れられません。
私も幼児期で覚えていませんが、母が「あんたのはしかはひどかった」と何度も言っていました。昔は、いろんな感染症にかかって生き延びた子どもだけが大きくなっていったのです。
1歳になったらはやくMRのワクチン接種をしてください。2回目の追加接種は小学校に入る前の1年間です。注射いたいよね、でも頑張ってね、これは君たちの命を守る大切な注射なんだよ、とご家族も励ましてあげてくださいね。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL