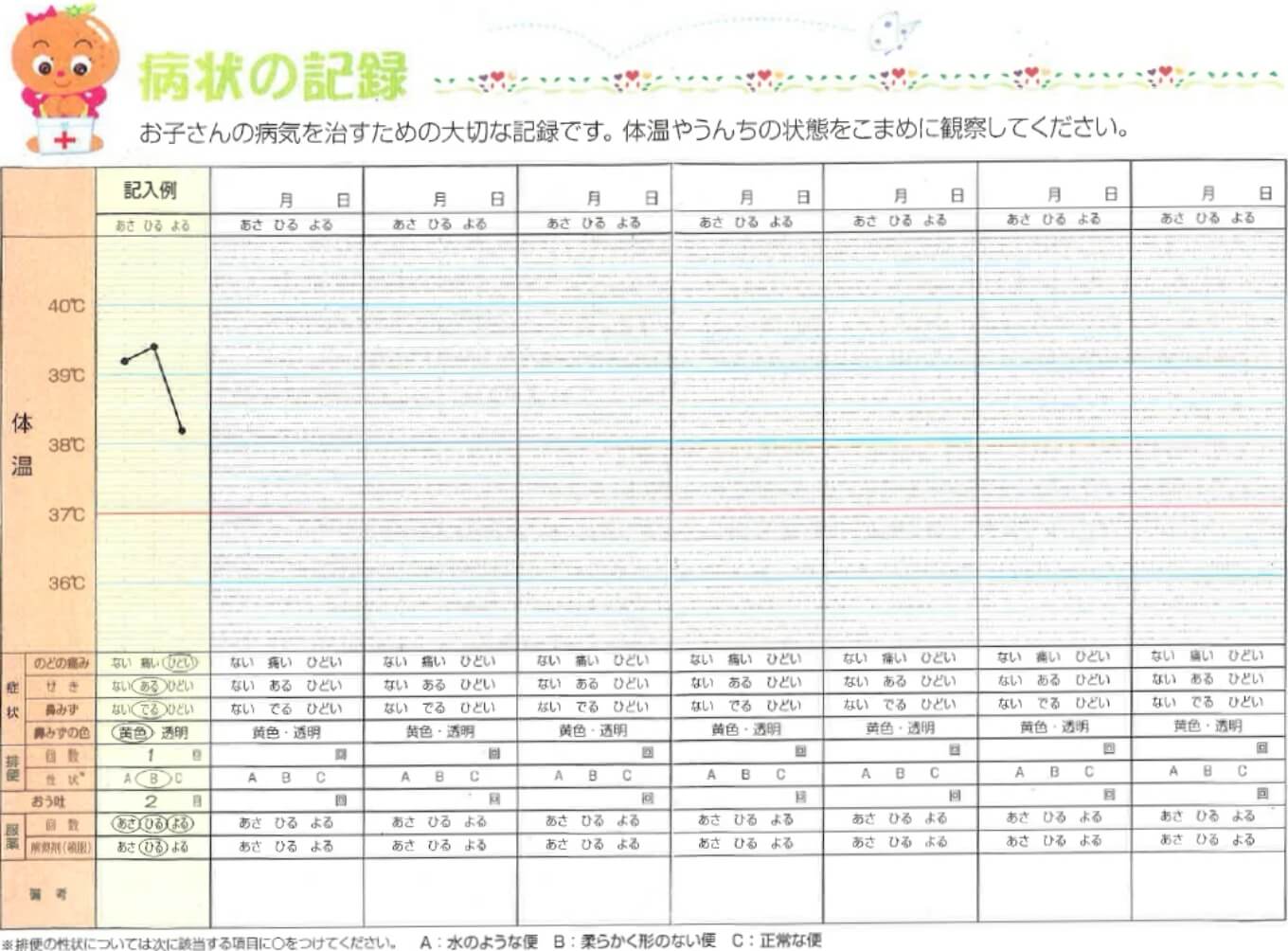今月の独り言
2023年終わり
今年の診療も無事12月28日で終了しました。
本当に大変な1年でした。9月まではしなければいけない外来コマ数が多く平日休みがなかったので体力的に大変でした。春から、コロナ、RSウイルス、アデノ、溶連菌、そのあとはインフルエンザも増えて、いっぺんに季節関連なく流行が続いたので、患者さんを診て、何を検査して何を処方するか、どう診断するか、ずっとアタマも使い続ける気力も大変な診療でした。年末には、元気だけど咳とゼイゼイが続く子が何人かいて、喘息の治療が効きません。かといって入院するほどの重症感もないのです。なんか変なウイルス感染による気管支炎と考えてますが、病院にいたらできる画像検査とか特殊検体検査とかできないので不甲斐ないことです。最終日までフォローしましたが年明けよくなってるといいなあ。
でもいつも力をくれるのは患者さんである子どもたちと、ご両親です。子どもたちはお気に入りのおもちゃやぬいぐるみを私に見せてくれて、いろんなお話をしてくれます。ありがとうね。ご両親も、長く通院して病気の理解が進むと、診察時に適切な病状の表現をして適切な処置をしてくれているので、なんか一体感を感じてうれしくなります。慢性疾患であるぜんそくやアトピー性皮膚炎や食物アレルギーは長いおつきあいになるし、日々の生活にかかわるので大変だけど、来年も患者さんと家族のお力になれるようにがんばろうと思います。安西先生とふたり体制になり、時間的余裕ができました。より多くの患者さんにお会いできるし、ゆっくりお話しできると思います。
来年も皆様にとりよいお年になりますように。
秋の漫画おすすめ
読書の秋です。小さいころから本大好き少女でした。文学もいいですが、漫画も大好き。家の本棚、1/3はお気に入りの漫画本です。
ちょっと前は「鬼滅の刃」が一番の推しで、完結するまで単行本を買い続け何度も読み、テレビアニメも映画もしっかり見て、診療所にいっぱい鬼滅グッズがあふれていたのはご存じの方も多いでしょう。あの世界観とキャラクターは今でも大好きですが、しっかり完結したのでひと段落。
今ハマっているのは、「葬送のフリーレン」です。少年サンデーに連載中ですが単行本は11巻まで出ていて、最近テレビでアニメも始まりました。フリーレンは1000年以上生きている魔法使いで、勇者と仲間とともに魔王を倒したその後、各地を旅していく様子が描かれます。ファンタジーなんだけど、フリーレンはじめキャラクターが魅力的。戦いや魔法の場面もいいし、泣けるんです。漫画の絵柄もとてもすてきなんだけど、アニメになると躍動感あって迫力あるなあ。
「SPY×Family」もいいですよ。少年ジャンプで連載中。単行本は12巻まで、これもこの秋からテレビでアニメ開始です。主人公の少女アーニャがかわいい。でも人の心が読める超能力者なのです。家族は血のつながりなく、自分の能力や仕事を隠すために疑似家族を形成しているという設定。父ロイドは実はスパイ「黄昏」で、母ヨルは殺し屋「いばら姫」。それぞれいろんな任務が課せられ、困難を乗り越えていきながら家族のつながりが深まっていきます。最近のアニメ放送では、豪華客船のなかでヨルがすごい戦闘シーンを見せていました。これも映像がとてもきれいです。
好きな漫画を読んで追っかけていると、人気でアニメ化されたという経過はこのふたつ同じで、アニメを見てはその場面の漫画本を読み返しています。だから忙しいのよ(笑)。文学本もおすすめがありますが、今日は漫画の話でおしまい。
アトピー性皮膚炎の新しい治療
アレルギーの治療は、この10年でずいぶん進歩しました。研究が進んで、病気の仕組みがわかってきたのと、それをもとにして新しい薬や、病気への向かい合い方の指導の変化も出てきました。
アトピー性皮膚炎は、20年くらい前までは、子どものアトピーにステロイドを使わないと公言する医者も多く、赤ちゃんの重症アトピーにワセリンだけで頑張らさせ、全身かゆくて掻いて傷だらけ、真っ赤になっていた子も少なくなかったです。そして、そういう赤ちゃんは、後からわかったことですが、経皮感作といって、バリア機能の落ちた皮膚から食物アレルゲンが入って複数の食物アレルギーになっていました。検査で食物アレルゲン陽性になると、卵アレルギーだから皮膚が悪化するのだ、と本人の厳しい食物除去と、母乳であれば母の食物制限もされていました。
2006年に二重抗原暴露説という新しい概念が提唱され、証明されました。これは今までのやりかたとまったく逆で、皮膚の湿疹が続くことで皮膚のバリア機能が落ちて食物アレルゲン陽性になるので早くから皮膚は治療してきれいにしたほうがいい、また食物アレルゲン陽性でも、食べられるものは早くから食べさせたほうが食物アレルギーにならないということです。
それで乳幼児にも積極的にステロイド外用薬を使って皮膚をよくしようということが学会からいわれてきました。乳幼児でもステロイドを使ってよくないわけでなく、多くの小児科医が使用経験がなく、どのくらい使って安全かを知らなかったのです。湿疹の程度によって効果のあるステロイドの強さを選択せねばならず、ひどいところに弱い薬を出しても効きません。また、チューブを1本出して、ひどい所に塗ってね、よくなったらやめてねというと、たいていの患者さんは、皮膚のぶつぶつにちょんちょんとぬるので効きません。皮膚の炎症は皮下で広がっているので、広範囲にしっかりぬらないと効果がないのです。当科では看護師がしっかり塗り方指導をして、効果を判定するため再診してもらいます。
ステロイドは塗ってよくなってもやめるとまた出てくることが多いのでそうなると、原因を調べたり、スキンケアをしっかり指導したり、プロアクティブ療法というステロイドをすぐ止めずに少しずつ減らす治療法にするなどとなります。最近はステロイドでない新しい外用薬が出て、コレクチム(デルゴシチニブ:JAK阻害剤)、モイゼルト(ジファミラスト:PDE4阻害剤)などで、いい皮膚をキープすることができ、ずいぶん楽になりました。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL