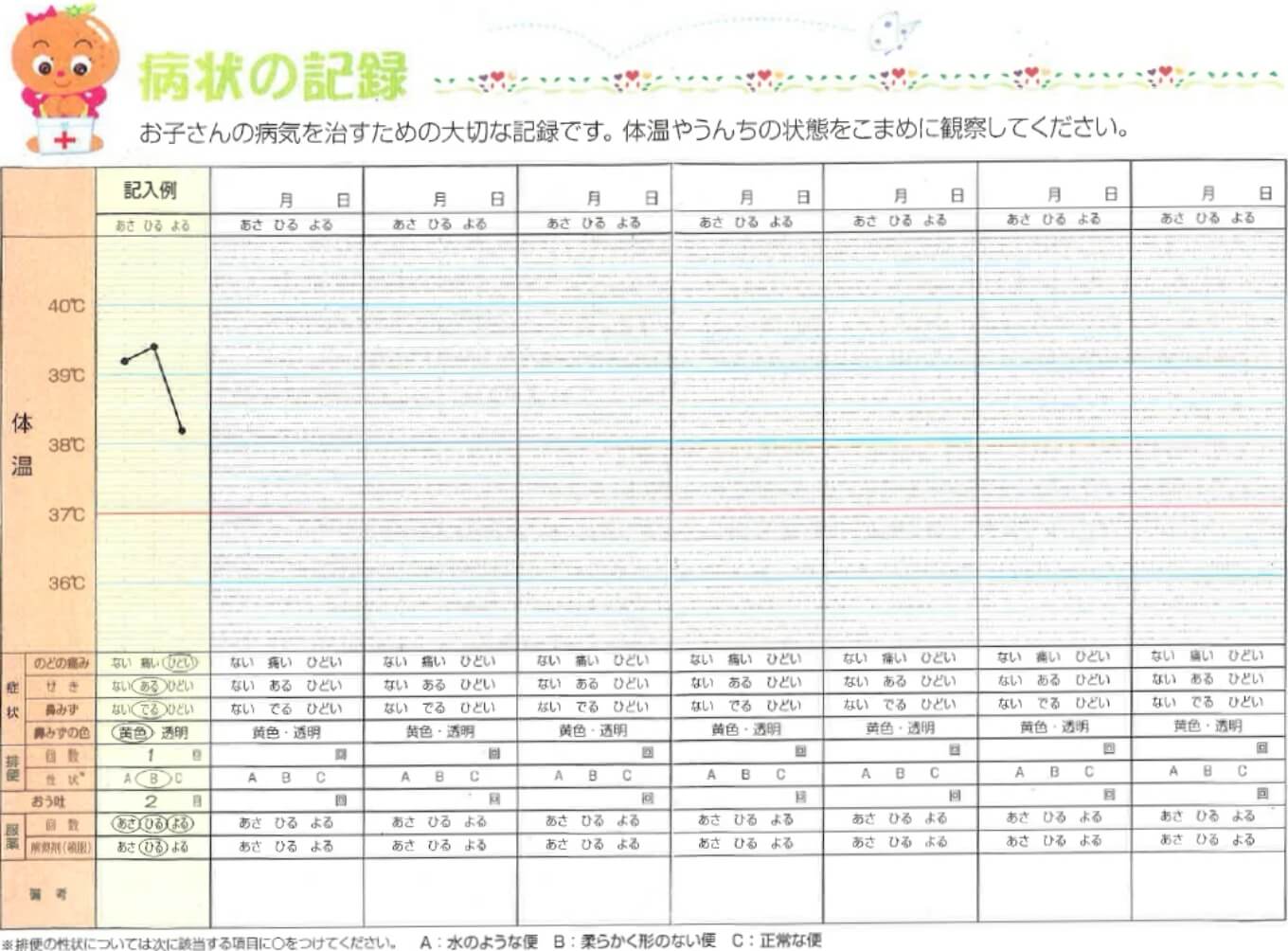今月の独り言
アトピー性皮膚炎の最近の考え方
医学の世界は、年々進歩があります。10年前は治療法がなかった病気に新しい治療ができたり、病気の原因がわかったり、病気がなぜ起こるか、どう進行するかにかかわる基礎的な研究が進んだり。なので、医者はいつも勉強して新しい知識を取り込まないと、患者さんのためになる治療ができません。しかし、開業すると、医者は自分ひとりですから、勉強をさぼっていればどんどん最新治療から取り残されるのです。
10年前まで、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎は、「乳児湿疹」という錦の御旗のもとに、放っておけば治る、ステロイドなんて使わない、1年くらいしたら自然に治る、と放置されていたのです。最近わかってきたことは、「皮膚バリア機能の低下」が湿疹やアトピー性皮膚炎の原因になるということです。さらに皮膚バリアが低下すると、いろんな物質が入ってくるので、「皮膚感作」といって、皮膚から侵入したアレルゲンでアレルギー反応がおこるということも注目されています。
赤ちゃんはもともと皮膚が薄くてもろいため、皮膚バリアが破たんしやすいのです。湿疹やじくじくがあれば早く治さないとどんどん広がり、そのうち食物アレルギーが進んでくる、ということが分かり、ステロイドも含め、早期に湿疹を治すことが大切なのです。放っておけば悪化して、湿疹は慢性化するとごわごわした皮膚になっていくし、何より皮膚のかゆみや不愉快さで赤ちゃんは眠りも浅いしいらいらして、健やかな発達が阻害されます。機嫌の悪い赤ちゃんに付き合うお母さんの苦労も大変なものです。昔は、卵アレルギーのせいでアトピー性皮膚炎がおこるとされて我々小児科医は食物制限をたくさんやっていましたが、今は逆で、アトピー性皮膚炎があるから食物アレルギーがどんどん進む、と考えられてきました。
最近来院された5か月の赤ちゃんです。2か月から顔の湿疹がよくならず皮膚科に行ったがワセリンのみでよくならず広がってきて、4か月健診でちゃんと治したほうがいいよと言われてある小児科に行った、すると、乳児にステロイドは使わない、放っておいてもよくなる乳児湿疹だから、ときっぱりいわれ、なんの検査もせず、離乳食で卵・乳・小麦を除去するようにと指示されたそうです。10年前なら普通だったかもしれませんが、アレルギーの治療が進んでいる昨今、それはないだろう?
食物アレルギーの研究も進んでいて、何でもかんでも除去することが最近の食物アレルギーを増やしているのではないかと反省期に入っていて、むしろ離乳食ではなんでも食べさせて、症状が出たものだけ除去しようというのが最近の我々アレルギー専門小児科医のスタンスです。この赤ちゃんも、弱いステロイドをしっかり1週間塗ったら皮膚はきれいになってぐっすり眠るようになり機嫌もよくなりました。検査ではTARCというアトピー性皮膚炎の検査値が上がっており、乳児湿疹ではなくアトピー性皮膚炎であることが証明されましたし、卵白に少し反応がありましたが、乳と小麦のアレルギーはありませんでした。
もちろんアレルギー専門医でなくても学会や研究会で新しい考え方を勉強して、ちゃんとステロイド外用で治療してくれる開業の小児科の先生も増えてきました。勉強しているかどうかが、治療法を聞くだけでよくわかります。患者さん方も医者を選ぶ知恵が必要です。2週間くらいやっても皮膚症状がよくならないとき、検査もせずにいろんな食物制限をいわれるときには、ちょっとおかしいなと思ってください。
今年も終わりです・・・
今年は秋から冬にかけて、マイコプラズマやウイルス性の肺炎が小学生を中心に流行しました。咳だけひどく、長く続くものから、熱が夜に上がって1週間も続くもの。胸部の聴診をしても異常がないのに、レントゲンをとってみると、肺炎だったり、気管支で痰が詰まって空気の入らない無気肺という状態だったり。これは、細菌以外で起こる、非定型肺炎というものの特徴です。薬も、今までの抗菌剤が効かなくなったり、ウイルス性ではまったく効かないので、よくなるのを待つしかなかったり。何人かはしかたがなく、入院をお勧めしました。でもまあ、何とか皆さん、熱が下がったり、診断をつけてお薬を出したりして最終日を終えてほっとしました。
今年はまた、「食べて治す」ということにも多く取り組んだ年でした。アレルギーの検査値のみで食物除去を指示する、というような医師は10年前に比べて減っていますが、いまだに難しいのは、「食べてみないとわからない」「食べるものによって違う」「人によって違う」ということです。
食品のたんぱく質はアレルゲンになる可能性はありますが、普通は、年齢とともに、消化吸収の能力や腸管で働く免疫力などによって、からだが受け入れる、「経口免疫寛容」という仕組みが働き、食べられるのです。アレルギーがあっても、微量のたんぱく質から少しずつ摂取してからだを慣らしていく「経口免疫療法」で多くは食べていくことができます。食物アレルギーの出方は、年齢によっても違うし、RAST値でも違うし、食品のタンパク量や加熱、混ざり方によっても違うので、ものすごく専門的経験がものを言います。
乳児で、RAST値は少ししかないので、医師からちょっと食べてみ、といわれて卵がゆでアナフィラキシーを起こした子もいるし、同じような数値で1歳過ぎて今まで食べていたのに急に乳の完全除去を言い渡された子もいる。3歳以上になるとRAST値関係なく食べられることも多く、小麦のRASTが100以上でもばんばんうどん食べてる子もいれば、10そこそこの数値でもうどん切れ端食べて1時間後に咳とじんましんが出る子もいる。はっきりいって食べてみないとわからないので、いかに安全に何を食べていくか、というのは、タンパク量も加味した詳細な指導が必要です。卵の数値が下がってきたので、卵の入ったものを少しずつ食べてみて、と医師からいわれたが、具体的に何をどれだけと言われないので、お母さんがイメージした卵の入ったもの、がマヨネーズで、1匙で蕁麻疹がでちゃった。マヨネーズは生なので、卵加工品の中でも最後にすべき食材なのですが、それは言われないとわからないよね。
いろんなびっくりしたことも多い1年でしたし、たくさん食物負荷試験もしました。診察室に入ってきて、あれも食べられた、これも食べた、とうれしそうに親子で報告してくれる患者さんたちが増えてきたことがよかったことです。みんなからも、かわいいお手紙や折り紙などなど、プレゼントありがとう。またこれらを励みにして来年も頑張ります。皆さまよいお年を!
喘息児の自立と支援
近畿各地の紅葉も盛りの頃です。11月21、22日は奈良で日本小児アレルギー学会学術集会に参加しました。学会長が天理よろづ病院の南部光彦先生で、彼は京大の先輩です。小児医療にものすごい熱意を持っている先生で、その思いのこもったプログラムや人選で、とても盛り上がりました。
私は、「喘息児の自立と支援」というシンポジウムの座長を仰せつかりました。
子どもの喘息は、7割が3歳まで、9割が6歳までに発症します。そして多くの患者さんは、よくなっていきます。薬がなくても発作が出ない状態を「寛解」と言いますが、喘息が良くなるすなわち「治癒」するというのはなかなかハードルが高くて、5年間寛解状態で、しかも呼吸機能や気道過敏性が正常である、ということになっています。半数以上の子どもたちは成人するまでに寛解しますが、成人してから再発するひともいるのです。私は必ず患者さんが6歳以上になると、呼吸機能や呼気NOによる気道過敏性の検査をし、薬を減らして治っていけるか、成人喘息に持ち越すタイプかを鑑別していきます。それが喘息治療の基本になっています。
成長するにつれ喘息の子どもたちは、精神的にも生活上も自立していくわけですが、それをどう支援するか、というのが今回のシンポジウムの課題でした。ずっと小児科で治療を続けてきて、どのタイミングで内科に引き継ぐかというのは大きな問題です。シンポジストは、小児科医、養護学校の先生、NPO患者団体の代表、それから心理学の先生でした。
進学や就職で実家を離れる時が、病院も変わり、小児科から内科に移行する時期ですが、かならずしもスムースに継続できないということ、初めての土地で一人暮らしになると、困った時の相談できる場所や医療機関が見つからないこと、自立をうながすにはもっと子どものころから困難を乗り越える力、自分はちゃんとやれるという自信をつけておくような心理的トレーニングが必要であること、という内容が提示され討論されました。
なかなか難しい問題です。お母さんに話して説明をするということが多い小児科医ですが、3歳以降になったら、子どもたち自身に話しかけ、ちゃんと説明をしようと改めて思ったことでした。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL