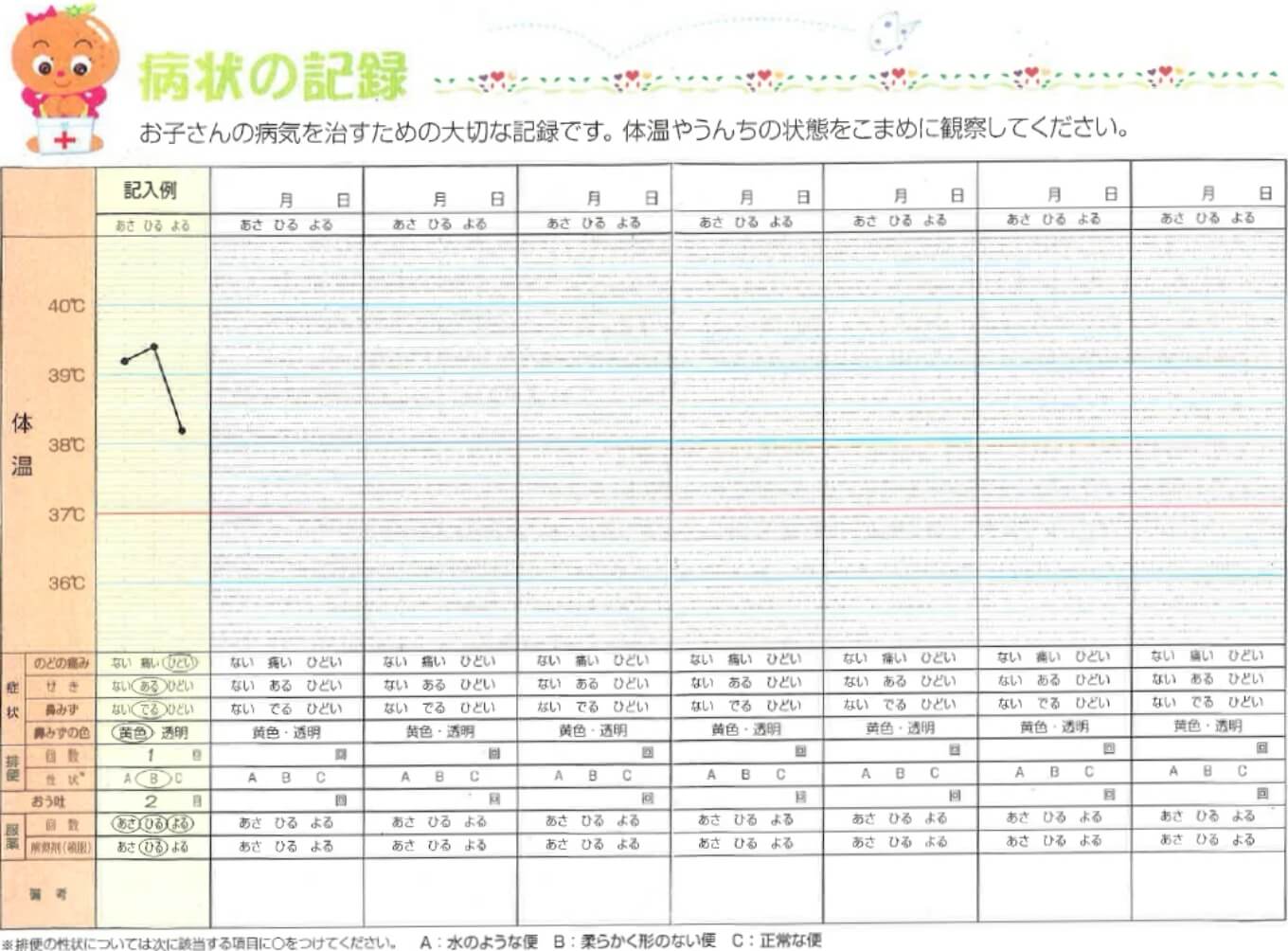今月の独り言
春に想うワクチン
子どもたちは春休みに入りました。周辺は桜が満開です。
ここにきていろんな病気が流行り始めました。寒い間はインフルエンザも含め、風邪も少なかったのですが、季節の変わり目となり暖かくなったり寒くなったり温度差が出てきたころ、2月末から、高熱が出る咽頭炎や、吐き気の来る軽い胃腸炎、鼻水だらだらの風邪などが増え、みんなウイルスです。先々週から0~1歳児のRSウイルス感染が続き、普通と違って咳や呼吸困難はそれほどひどくないのですが高熱が5日くらい続きます。保育園で流行しているようです。幸い重症になる子は少ないのですが、2週間で3人が入院となりました。
私が医者になったころ子どもたちに重症の病気をもたらした感染症は今、ほとんどがワクチンによって予防できるようになりました。研修医の頃当直をしていて、夜に乳児が発熱と痙攣で来たら、必ず髄膜炎を疑って、髄液検査をして細菌培養をして診断がつけば夜中のうちに抗生剤の治療を開始していました。診断と治療が遅れると死亡や後遺症の率が高まるのです。髄膜炎の起炎菌の大部分を占めていた肺炎球菌、インフルエンザ菌は今ワクチン接種で激減し、ワクチン前は年間700人以上だった発症が、最近では10人前後の発症になっています。研修医1年目の頃、麻疹(はしか)にかかって脳炎をおこし、昏睡状態で病院に転送されてきた女の子は一度も目覚めることなく1週間で亡くなりました。出産まじかに水痘にかかったお母さんが出産した赤ちゃんは新生児水痘で重症化し脳炎になりました。先天性風疹症候群の赤ちゃんも産科から回ってきました。生まれつき心疾患と目に異常があり、いまではできる聴力検査も当時はなくて確認できませんでしたが聴力障害もあったかもしれません。当時はみな、運命と思ってあきらめるしかなかったのです。今は麻疹、風疹、水痘、みなワクチンで予防が可能です。小児科医としては本当に子どもたちが元気に育ってくれてうれしい時代になりました。
副反応が怖くてワクチンはいやだという意見もあります。実は副反応のないワクチンはありません。しかし副反応の確率は非常に少なく、ワクチンをすることにより社会全体で得られる利益が勝るので行う必要があるのです。ワクチンも次々に改良され、副反応の少ないものが開発され、変わっていきます。日本は先進国の中ではワクチン後進国で、安全なものを後出ししていますので、今やられているワクチンはほぼ安全でお薦めのものばかりです。どうぞスケジュール通りに定期接種を受けてくださいね!
食べられなくてもいいか・・・
2月に入ってから、年度替わりを控えて、アレルギーの検査・診断・診断書や生活管理指導表の記入などを求めて患者さんが増え、忙しくなってきました。
最近の食物アレルギーの考え方は、アレルギーの検査値が高くても1歳過ぎたら負荷試験をして、早くから食べていこうというのが主流です。しかし何をどのくらい、どういうふうに安全に増やしていくか具体的な指導をしていくのには知識も経験も必要です。いつも重症の卵のアレルギーの子どものお母さんにいうのですが、卵料理が食べられなくても、卵の入ったパンやお菓子が普通に食べられ、揚げ物やハムやかまぼこやハンバーグに卵が入っているかおびえながら外食を選んだり避けたりする必要がなくなれば、ずいぶん生活は楽になるんじゃない?と。卵成分が何にどのくらい入ってどのくらい加熱されているかがわかれば安全に食べるものを増やして行けます。が、続けることが重要なのです。
しかし最近は働いているお母さんが増えて、忙しい方も多いせいか、食べ物が増えていく様子を3か月に1回くらいは受診して聞かせてもらって増やすやり方を進めていきたいのだけど、この時期半年ぶり、1年ぶりという受診の患者さんも多く、あまり食べるものが増えていなかったりやめてしまったりしている方も少なくありません。子どもたちも大きくなると、卵や乳の入ったものやそのものをずっと食べ続けることを嫌がり、お母さんとけんかになったりします。最近は、そんなに嫌な思いをして、家族関係が悪くなったりして食べることが苦痛なくらいなら、やめてもいいのではないかとも思うようになりました。
今のところ、アレルギーのある子どもが食べられるようになるには少しずつ食べ続けるしか方法はないので、将来のことを思って食べられるようになったほうが便利で安全だよ、と言っていたのですが、まあ10歳にもなる子が、もう食べんでいい、と宣言するのであれば、それもまた選択肢だよね、と。
もちろん親子でがんばって何年もかかって、小麦、卵、牛乳、とひとつずつ克服している患者さんもいます。患者さんの生活や考え方や日常の優先順位はそれぞれ。一番いいやりかたを相談しましょう。
ちょっとうれしい科学ニュース
コロナについては憂鬱な話しかないので今回は別のお話をしますね。
コロナ下でも希望が見えて明るくなった話題がいくつかありました。
ひとつは小惑星探索機「はやぶさ2」が、6年50億キロの旅を終えて昨年12月に帰還したこと。ふたつめは最近ですが、駿河湾沖の水深2200mから、体長1.4m、体重25kgの新種の深海魚が見つかり「ヨコヅナイワシ」と命名されたこと。みっつめは、恐竜好きにはうれしい話、「ディノ・ネット恐竜展示館」がオンライン公開されたことです。
私は生物が大好き。ペットとしての動物が好きなのではなく、生物として存在しているいろんな種に興味があります。ミジンコでも面白いよ!だから動物園も水族館も、古代の生物が展示されている博物館も大好き。何時間でも過ごせるし、知らなかったいろんな生物の存在や思いがけない生態を知ると楽しいです。滋賀県に住んでいるのですが、県立琵琶湖博物館という施設があって、琵琶湖に関する地層、古代の歴史、生息する昆虫・魚・水生生物・鳥・植物・動物、それにまつわる人間の生活などに関する展示や知識の提供があって、小学生わくわくの博物館です。環境変化や外来種の台頭などで、絶滅に瀕しているいろんな動植物も多いのですが、それがなぜか、どういうことが理解できれば昔ながらの固有種を守れるかという、これからの世代への問題提起もあります。
恐竜はもともと小さい頃から大好きで、クリニックにもいろんな展示をしています。子どもってだいたい恐竜が好きで、皆さん恐竜の絵のついたシャツを着てきたり、お気に入りのフィギュアをもって来てくれます。ありがとうね、みんな!あんな大きな生物が、地球上に1億6000万年も繁栄していたって、興奮しません??約6600万年前に、鳥類を残して絶滅してしまったのです。それが、いろんな化石からいろんなことがわかってくるんですよ。なんて面白いんでしょうか!
さてコロナ下で博物館に来てくれる恐竜ファンも減ったせいでしょうか、国立科学博物館が、各地の博物館と協力して、「ディノ・ネット恐竜展示館」をオンライン公開しました。(http://dino-net.jp/) ここでは、いろんな恐竜骨格標本を3Dで、あちこちから詳細に観察できる。専門家からの解説もある。博物館をバーチャルで探検することもできます。閲覧無料です。恐竜大好きの方はぜひのぞいてみてください。2月の毎週土曜日には、恐竜の専門家が解説するオンライン講義もあって、これは有料で予約制ですが、科博の真鍋真先生やカムイサウルスを報告した北大の小林快次先生がお話してくれます。これはかなりわくわく。
私は生まれ変わるなら、鳥になりたい、できればフクロウかワシになりたいです。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL