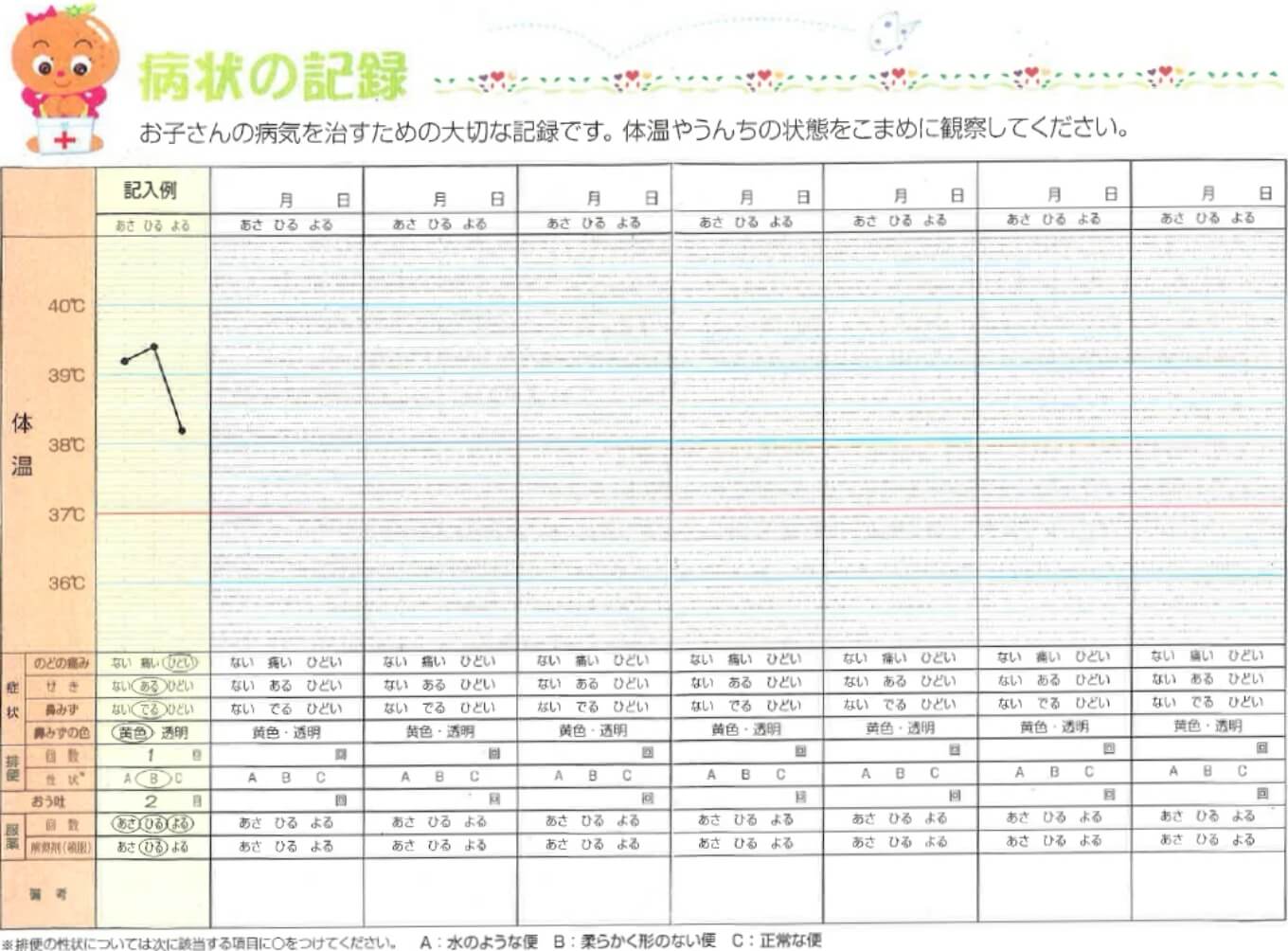今月の独り言
ひとりごとも最後です
2025年も押し迫り、12月27日で仕事納めとなりました。インフルエンザの流行が今年は早かったですが、その分、年末は落ち着いた外来になりました。
さて来年2026年5月で、かめさきこども・アレルギークリニックは開業20年となります。済生会中津病院小児科でアレルギー外来をやっていましたが、その当時アレルギーの専門医療をやっている小児科医は少なく、多くの子どもたちは専門医療を受けられていませんでした。開業して毎日地域の子どもたちの外来をすれば、何倍もの患者さんの役にたつかなと思ったのです。
当時アトピー性皮膚炎の治療に、子どもだからステロイドは使わないという医師も多く、全身湿疹でかゆくてじくじくで夜も眠れない子どもがたくさんいました。そういう子どもたちの皮膚バリア機能が悪いせいで食物アレルギーとなり、卵・乳・小麦完全除去、なんていう乳幼児がたくさんいました。今は、早くから皮膚をよくすることができ、ステロイド以外でもいい薬がたくさんあります。乳児期早期に皮膚をよくすることで、ホントに重症の食物アレルギーは減りました。気管支喘息も、長期管理に、ロイコトリエン受容体拮抗剤(モンテルカストやプランルカスト)が広まると発作が減り、また乳幼児も使えるステロイド外用剤が増えて、子どもの喘息発作や入院は本当に減りました。子どもたちや家族に、かゆみや湿疹、喘息発作のしんどさ、食べるものの制限がある不便さ、こういうもののない生活がしてほしかったのです。今はそれぞれの疾患にガイドラインができ、アレルギー専門医でなくても標準治療を実践する若い小児科医が増えてきました。アレルギーで悩む子どもたちや家族が減ったのは本当によかったです。
そういうわけで私のめざした小児医療はずいぶん浸透してきました。開業20年をきっかけに、私はクリニックの院長を辞し、外来の日数も少し減らそうと考えています。年をとると体力が落ち、集中力や忍耐力が落ちてくるのを感じています。仕事でミスをしたり余裕がなくて患者さんに優しく接することができなくなるのが心配なのです。まだまだお役にはたてるとは思いますのでもうすこしがんばります。
ホームページも変わっていきますが、まずこの今月のひとりごと、長年つぶやいてきましたが、役目も終えたので今月でお終いにしようと思います。長年読んできてくださった方、ありがとうございました。
インフルエンザ
インフルエンザが大流行です。今年は流行時期が早く、ワクチンが間に合わない人も多いです。10月半ばから、地域によっては学級閉鎖が始まりました。
11月は小児科一般の外来はインフルエンザに占領されています。ある平日朝の小児科受診40人中、発熱は30人で、そのうちインフルエンザの検査陽性が20人、他院で陽性とされ熱の続いているひとが5人いて、そのほかの発熱は5人のみでした。
インフルエンザは初めから高熱で、それが下がらずにずっと続くことが多く、患者さんはぐったりしてぼうっとしていることが多いです。高熱で熱性けいれんが起きることもあります。先週は待合室でけいれんを起こした子がいて、けいれんは止まったけれど意識の回復が悪かったので、救急車で病院に紹介入院となりました。
今はインフルエンザの薬があります。ウイルスの増殖を抑えるノイラミニダーゼ阻害薬といって、タミフルが有名です。1日2回5日間飲まねばなりませんが、古くからある薬でエビデンスも多いし、昔は異常行動との関連を疑われましたが、異常行動はインフルエンザ自体の症状であって、薬のせいではありません。熱が下がってからも薬を飲むのは面倒かもしれませんが、一番効果があり、信頼がおけます。
イナビルといって吸入1回でいいという薬も出て、1回ですむので人気ですが、ちゃんと吸えなければ効きません。これは、薬局で薬剤師が指導してちゃんと吸えることを確認することが義務づけられています。それでも薬の吸入なんてやったことがないと、大人でもうまく吸えません。吸えたはずなのに熱が続くという小学生が何人もいました。今日来た6歳の幼稚園児は休日開いている診療所でイナビルを出されて、家で吸ったけどうまくいかなかったと母。薬局で実際に吸っていないのです。熱はそれから4日間続いています。処方箋をもっていったのは大手薬局のチェーン店ですが、アタマにきて電話しました。そしたら、感染予防の点から、店頭ではしなかったがちゃんと親に吸入の仕方を説明したというのです。一般のひとや子どもがいくら口で説明されても吸入ができるはずがなく、吸えてないのを薬剤師が横でみて、何回も指導してやり直して吸うからなんとか薬が入るのです。薬局なんだから、感染予防なんて言い訳にならないでしょう。ちょっとあきれてしまいました。こういうこともあるので私はなるべくイナビルは処方しません。
ゾフルーザといって1回で飲むだけですむエンドヌクレアーゼ阻害剤も最近出た薬です。これも効けばいいのですが、まだエビデンスが十分でなく、私は処方しませんが、ちょっと効き目はどうかなという気がします。
昔はインフルエンザは薬もなく、検査キットもありませんでした。皆、自分の免疫力を頼りに家で1週間熱に苦しんで過ごし、中には脳炎や肺炎など合併症で命を落とす人もいたのです。今は薬で早く治るので夢みたいです。皆さん、元気で頑張りましょう。
ワクチンで・・・
私が小児科医になった40数年前は、ワクチンは一部に限られ、効果も不十分でした。子どもの病気は大多数が感染症で、それで亡くなったり、後遺症が残ったりすることが多かったのです。小児科医の仕事は感染症との戦いでした。
麻疹(はしか)は、どんな子どもも一度はかかるもので、「はしかみたいなものだ」という慣用句は、だれもが一度は若い時期に経験するもの、という意味でよく使われていました。ワクチンが始まったのは1972年で私の研修医時代はもうずいぶん減っていましたが、1回接種だったので十分な予防効果はありませんでした。医者になって初めて担当した死亡した患者さんははしかの脳炎の女の子で、けいれんがとまらず、入院して亡くなるまで意識は戻りませんでした。水痘(水ぼうそう)になると、全身みずぶくれの発疹がたくさんできて、きれいに治るか心配だったものです。流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、耳の下が腫れて痛いのですが、病気自体より合併症が問題でした。髄膜炎は多かったし、男子では精巣炎で睾丸が腫れて、無精子症になる人もいました。最近では、聴力障害が後遺症で多いことがわかってきました。風疹(三日ばしか)は、病気自体は軽いのですが、妊婦が感染すると胎児に影響が出て、先天性風疹症候群(心疾患、難聴、白内障など)の赤ちゃんが数多く生まれていました。あとからではどうしようもないのです。百日咳も乳児がかかると呼吸障害がひどくて命にかかわります。2か月になったらすぐワクチンです(5種混合)。
研修医のころ、乳児の髄膜炎は重症な病気で、それを起こすインフルエンザ菌は今ワクチンで激減しました。乳児の髄膜炎は1/3は死亡し、1/3は後遺症が残り、回復するのは1/3でした。ロタウイルスも重症な胃腸炎を起こす病原体で、乳児がかかると重症化しやすく、長いあいだ点滴治療が必要です。伝染力が強いので、病室がまるごと隔離部屋になり、6~8人の乳幼児がまとめられ、「ロタ部屋」と呼ばれていました。
これらの感染症は、ワクチンの普及によってもうほとんど見なくなりました。若い小児科の先生方は教科書でしか知らないでしょう。本当にありがたいことです。でも、日本は恵まれていますが、多くの開発途上国ではまだ多くの子どもたちが予防できる感染症で死んでいるし、大人の戦争によって死ぬ子どもたちもたくさんいます。子どもたちの命は健康は、大人が守らねばならないのです。

 待ち時間
待ち時間 TEL
TEL